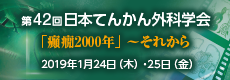連絡事務局
株式会社 コンベックス
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 5-12-1
虎ノ門ワイコービル
TEL : 03-5425-1602
FAX : 03-5425-1605
E-mail :
stereo2019@convex.co.jp
ご挨拶
第58回日本定位・機能神経外科学会
会長 谷口 真
(東京都立神経病院 脳神経外科 部長)

伝統ある日本定位・機能神経外科学会の第58回学術集会のお世話をさせていただきます東京都立神経病院 脳神経外科の 谷口 真です。この事は私個人のみならず、私の所属する神経病院、なかでも定位脳手術チームにとって大変な名誉であり、チーム一同で精一杯務めさせていただきますのでよろしくお願いします。神経病院は、1980年に開院しましたが、この病院は、定位脳手術と少なからぬ縁を持っており、手術室の基本設計の段階からすでに楢林博太郞先生や大江千廣先生などの大先輩達から定位脳手術を前提とした御指導を頂戴したと伺っております。また、本学会との関係を見ても、1986年の第25回に初代部長の石島武一先生が、また2006年の第45回に2代目部長の高橋 宏先生が会長を務めておられます。しかし私が初期研修を終わって神経病院にはじめて赴任した昭和も終わり近い1985年頃、脳神経外科の世界は、機能的定位脳手術にあまり追い風ではなく、神経病院でも本態性振戦の患者さんに年に1件ほど細々と視床手術が行われていた程度でした。その頃は私自身、まさか自分が将来この病院に戻りさらに、この領域に手を染めることになろうとは想像すらしておりませんでした。
私が大学を卒業した頃は、調度画像診断が脚光を浴び始めた時代です。すでにCTスキャンはどこの病院にもあり、また私が臨床研修開始したまさにその年に東大病院でMRIの臨床治験がスタートしました。これら画像診断技術が脳神経外科の臨床に与えたインパクトはすこぶる大きく、私にとっては、脳神経外科医になった最初の日から、「脳神経外科の病気とは目に見えるもの、脳神経外科医はそれを取りに行く人」でした。一方で当時の定位脳手術はまだ脳室造影とアトラスに頼ったターゲッティングの時代です。しかも狙う先の構造も脳の深部にある小さくて耳慣れないものばかりです。突然「ゼンコーレン」だの「コーコーレン」だの言われても、そもそもなんのことやらピンときません。しかも誰に聞いてもそれが何をする構造なのかはっきりした返事がかえってきません。また、どんなに目をこらして画像を見ても、どこに病気が有るのか姿が見えません。「いったい何をしているのか皆目わからない」。こういう漠然とした不安が当時駆け出しの脳外科医であった自分にこの領域に積極的に参入するのをためらわせた最大の理由だった気がします。そもそも、あんな小さい穴から、アトラスと称する誰ともしれない脳で作った地図ひとつを頼りにあの深くて小さな構造に本当にたどり着けるのだろうか?また、たとえ小さな凝固巣とはいえそこにある一見正常にみえる構造を破壊して本当に大丈夫なのだろうか?そしてなによりもどうしてそこに凝固巣を作ると治療効果が生まれるのか?そもそもこれは単なる経験則なのか、それともその根拠となる病気の発生機序がわかった上でやっていることなのか?ともかく手法の面からも理屈の面からもたくさんの「はてな」が頭の中を駆け巡るばかり。何だか難しい高尚な事をやってるらしいとわかっても、それを支える基盤技術なり理論が未成熟過ぎて、私のような脳外科になりたての小僧には、自分のこの先の職業人生をかけてその中にどっぷり漬かるにはあまりに怖すぎる領域という印象でした。もし今の自分がタイムマシンに乗ってもう一度当時の自分に戻ったとしても、やはり時代の状況を考えると自分がこの業界に深入りすることは無い気がします。つまり、定位脳手術の黎明期にそれに手を染めた人達と、今、定位脳手術をやっている人達は、もしかしたら根本的に人種が違うのかもしれません。
もう一度、この領域に出会うのは、自分が1997年に再び神経病院に戻った時で この間約10年が経過しておりました。実はこの10年とは、機能的定位脳手術の世界では100年に一度と言えるほどの大規模地殻変動が起こった時期で、私は、はからずもその直前と直後の世界を同じ場所で経験する事になったわけです。少し前の1992年には、 Laitinenn の後腹側淡蒼球の破壊手術の報告があり、ドパミンの登場とともに一度は過去のものになったと思われていたパーキンソン病に対する定位脳手術が、その後行き詰まった薬物療法長期投与の問題点の新たな解決手段として再び脚光をあびるようになっていました。またMRI targeting の導入もこの頃であり、脳室造影とアトラスによる targeting には抵抗のあった画像診断時代の脳外科医にも手術プロセスそのものが相当受け入れやすいものに進化していました。また、調度この頃は、破壊術に替わる可逆的治療手段としてDBSが登場し、本邦への導入ももはや時間の問題といわれていた時期でもありました。
調度私がドイツに留学していたときにベルリンの壁が崩れましたが、歴史が動く時というのは、大体こういうものの様で、それまで一見永遠に変わらない不動のように見えたいろいろの物事が突然一気に変わります。今回は、定位脳手術の世界で偶然その瞬間に遭遇したわけで、その後、その中であれこれとやっているうちにふと気がついてみたらいつの間にか20年が過ぎておりました。この間、パーキンソン病や振戦などに対するいわば古典的定位脳手術のDBSによるリバイバルのみならず、従来手を出しにくかった遺伝性全身性ジストニアに対する淡蒼球DBSの劇的な治療効果など新しい知見を世界と同時進行で体験することができ、本当に刺激にみちた日々を過ごさせていただきました。幸い、その途上では、同じ道を目指す診療科や専門領域を越えた多くの仲間にも恵まれ、脳外科医となってはじめてチーム医療という言葉の意味を本当に理解出来た日々でもありました。
しかし、その20年を過ぎて今、ふと頭をよぎるのは、この間自分は、いったい何をしてきたのかというという疑問とも後悔ともつかない複雑な思いです。偶然自分は機会に恵まれていろいろな体験をしたが、はたして自分は、その機会を与えてくれた科学の歴史に対して何か貢献をしたのか?言葉を換えれば自分は歴史の中になにか「歯型」を残したのか?自分は常に患者の安全を言い訳に自らも安全運転に徹した科学の単なる消費者で終わるのか?先に、自分を含め今定位脳手術に携わっている多くの脳外科医は、昔とは人種が違うと書きましたが、少なくとも神経科学の正統な探究者だったという点では、昔の定位脳外科医は自分が到底及ばないくらい熱意と意欲と冒険心にあふれた人達だったのではないでしょうか。もちろん正統な科学の手法に基づいた事実の把握と検証、論理だった推論の末の科学上の「冒険」は、「無謀」とは全く別物と言う事は十分承知していますが、われわれは「無謀」を避けるを免罪符に、この「冒険」までやめてしまっていないでしょうか?
今回のポスターは、中世の海図を定位脳手術のアトラスに見立てています。外科医は中世の船乗りです。地図もあやふやで、GPSもなく、通信手段もろくに無かった時代、航海の先に何が待ち受けているのか不確かだった時代、命を賭して海に漕ぎ出て行った船乗り達は、一体何を目指していたのか?多額の日当、おそらく船長クラスには名誉と収入の両方、またあるものは軍人として国の将来を背負って、いろいろ理由はあったでしょう。ただ、いずれにせよ、どこに何が潜むかわからない、はたして生きて戻れるかわからない未知の海に彼らを駆り立てたものは、お金や名誉だけではなかったのではないか?未知なるものへの好奇心、探求心、冒険心、どこか彼らを駆り立てた力の根底にはそれがあったのではないか?
現在、医療制度も医学研究制度も大きな変革の中にあり、臨床現場で新しい試みを実現するのは日増しに難しくなりつつあります。ともすれば倫理委員会の審査は前例探しや海外の動向の確認に終止しています。臨床現場には、クリニカルパスというもともとは工場の生産管理手法に端を発したシステムが導入され、医療行為はまるで完成品の製造産業のような扱いを受けています。しかし、今ようやく脳の未知の領域に踏みこんだばかりの私たちの学会が扱うテーマをこれと同じ物差しで評価して良いのか?そもそも機能的神経外科に携わる脳神経外科医が、すでに確立した治療領域の中だけに満足し、外にある未知の病気の世界、もしかしたら自分がその治療に寄与できる可能性のある領域に思いを馳せず、単純に自分のあてがい扶持の中だけで満足して暮らすようになったら、これからの神経科学の世界は小さくなる一方。本当は、世の中には、もしかしたら自分たちが役に立てるかもしれない無限の世界が広がっているのに。ニューロサイエンスは現在急速に発展しており、その知見は日々拡大しています。そして機能神経外科医には、患者の脳の一番近くに立つ者として脳の機能そのものの探求者の一翼を担い、未知の世界への新しい航海を始める冒険者としての役割が期待されています。いろいろの医学領域で現在 from bench to bedside という言葉が用いられますが、ニューロサイエンスの世界では、われわれこそがまさにこの橋渡し役です。だから今、こういう時代だからこそ機能外科に携わる我々は、中世の船乗り達のDNAを少しでも受け継ぐ必要があるのではないか?そんな思いから、今回はメインテーマに「脳神経外科医が果たしたニューロサイエンスへの貢献」という、なんだか演題が出しにくいテーマを掲げさせて頂きました。機能外科の歴史で「歯型」を残した誰かの話をしていただいても結構です、自分の残した「歯型」の自慢話でも結構です、これから「歯型」を付けようとする人の抱負を込めた途中経過報告でも結構です。ともかく、自分はニューロサイエンスに一枚噛んでるぞという旗揚げのつもりで気軽に演題を出してください。ここでの発表が航海の第一歩であっても一向にかまいません。
もちろん、このほかにもいくつかシンポジウムを設定しております。シンポジウム2では、「パーキンソン病 治療手段多様化時代の DBS」を取りあげます。すでに進行期パーキンソン病に対するDBS療法が本邦に導入されて20年近くになりますが、この間、薬剤療法も時々刻々と進化し続けておりこれに伴ってパーキンソン病治療戦略そのものが変化し続けております。手術の事だけを考えていたのではこれからの外科の占める役割は見通せないので、今回は、神経内科でパーキンソン病を専門にしておられる先生方をお招きし、主に二つのテーマをディスカッションしたいと思います。一つは、多様化したパーキンソン病の薬物治療の現状、中でもContinuous Dopaminergic Stimulation について御説明いただき、これに伴って今後パーキンソン病治療戦略がどのように変わると予想されるのかについてお話しを伺いたいと思います。もう一つのテーマにDBSの刺激調整の問題を取り上げます。パーキンソン病のように経過の長い病気について、患者さんの人生の長い時間の中で外科医と共有する時間は限られています。また、いかにDBS が効果的な治療法であっても、それだけでパーキンソン病患者さんのかかえる問題がすべて解決するわけではありませんし、投薬の継続も必要です。神経内科医は、手術の前から後まで、われわれ外科医と比較にならないくらい長い時間を個々の患者さんと共有します。DBSの術後の患者さんについては、手術が終わるとDBSの刺激条件調整と、薬の調整といういわば二つのダイヤルが存在することになるわけですが、それぞれを誰が管理していくのが患者さんにとって幸福かは、今まであまり議論されずに来ました。そろそろ登場から20年になろうとするパーキンソン病のDBSですが、今でも一部の例外を除けば、神経内科全般としては、刺激調整から距離を置きたがる先生方がまだまだ多い様に見受けます。なぜ神経内科の先生の多くは、刺激調整にそれほど身が入らないのか、また少数派の刺激を自らおやりになって下さっている先生方は実臨床の現場でどのような困難を感じておられるのか?われわれの側の体感温度との違いにはそれなりの理由があるはずです。それを、我々の側ではなく神経内科の先生方の側からお話しいただくのは、今後この治療手段を根付かせ、より多くの患者さんの幸福に結びつけるために大変参考になろうかと思います。
シンポジウム3では、古くて新しいテーマ、疼痛外科を取り上げます。米国では、1990年から99年に国策としての脳の10年がありこの間にニューロサイエンスが長足の進歩を遂げました。続いて2001年からの10年は疼痛の10年でしたが、この間、疼痛のメカニズムについての研究は大幅に進みましたが、創薬のレベルでは、まだまだ研究成果を臨床現場に充分に還元できる段階に至っていません。それどころか、90年代後半からの非がん性疼痛に対する医療用麻薬の使用制限緩和は、現在多くの過量投与患者を生み出し、それが社会生産性に与えている悪影響はすでに看過し難く、米国は、大統領に「戦争」という言葉を用いさせるほどになっています。歴史を振り返れば古くは、難治性疼痛は、外科の領分で、疼痛のメカニズムがまだ充分わかっていない時代には、手探りながらいろいろの外科的除痛の試みがなされました。疼痛治療に携わった外科医達は、数多くの失敗を積み重ねながらもいくつかの分野では効果的な除痛手段を生み出してきました。三叉神経痛に対する微小血管減圧術や腕神経叢引き抜き損傷後の上腕痛に対する DREZ-lesion、骨盤内悪性腫瘍の末期の疼痛に対するmidline myelotomy などはその成果の一部です。神経障害性疼痛という概念が定着し、そのメカニズムに立脚した治療手段にも陽の光が当たり始めている現在、薬の要らない、もしくは薬を大幅に減らすことの出来る治療手段として、疼痛外科が難治性疼痛の治療戦略の中で新たな役割を獲得する日は近いのではないかと思います。ともかく、ヒトの痛みの問題を、動物実験だけでは解決しきれないのは明白で、この意味で疼痛に苦しむ患者とともに戦う外科医のはたす役割は大きいと考えています。皆様の演題をお待ちしております。
シンポジウム4では、昨年に引き続き精神機能のニューロモデュレーションについて取り上げます。昨年の奈良での大会で明らかになったことの一つは、本邦でもようやく精神科領域の疾患を脳の機能の問題として外科治療について討議する事のできる土壌が生まれつつあるという事実でしたが、まだまだ過去の影響は大きく、いざ実践となるとハードルが相当高いのが現状です。諸外国と異なり、この10年近く、我々は毎年のように学会の場で同じような議論を繰り返してきまいたが実際には何も始まっていません。要するにまだ我々のこれまでの知見や治療成果が、精神神経科の先生方に行動を促すほどのインパクトを提供できていないということになるのでしょう。しかも精神科領域の疾患を扱うにあたっては、その治療ゴールを単に疾患の重症度のスコアが改善するかどうかだけでなく、その後手術を受けた患者が社会の一員として復帰出来なければ結局意味が無いと言う、これまでに我々が扱ってきた疾患以上に高いハードルを要求されます。そこで今回は、精神機能のニューロモデュレーション治療のゴールをどこに設定するかという点をひとつの論点として精神神経科の先生方や医療倫理学者も交えて討論したいと思います。
シンポジウム5では、パーキンソン以外の不随意運動を呈する疾患に対するDBS治療を取り上げます。もはや古典的なテーマですが、近年、多くの不随意運動を呈する遺伝性疾患、なかでもジストニアについて遺伝子の特定が進み、特発性・二次性という従来の疾患境界が少しずつ不明確になってきています。また、一度完成した運動制御系がその後に破綻して問題を起こす成人の疾患群と、成長期で運動制御系そのものが発展途上にある段階で発生した問題によって起こる小児のジストニアでは疾患の理解そのものに違う視点を導入する必要があります。今回は、さまざまなジストニアに対するDBSの治療反応性の経験をこの問題の理解に組み入れて神経小児科・神経内科で長くジストニアの治療に協力して下さった先生方から基調講演を頂戴します。
なお、これらシンポジウムは、基調講演として当方が指定する演者からもお話しを頂戴しますが、もちろん一般の会員からの演題応募も歓迎しております。どうぞ奮って御応募下さい。
臨床医学の進歩に外からの視点というのは大変重要で、ともすれば内向きになりがちの専門家集団の議論に学際領域からの多くの先生方をお招きし、時には辛口の意見を頂戴してお互いに議論するということが重要な出発点です。今回は、神経病院という専門病院の特色を生かして、国内外から定位脳手術に関連する学際領域の多くの先生方をお招きしました。定位・機能神経外科学会も法人化され、従来身内であるはずの多くの脳外科の先生方からそう見られていたようなちょっとオタクな同好会の印象から、少なくとも外見だけは、その活動成果によって社会に貢献する専門家集団に成長しつつありますが、それを構成する一個一個の細胞である我々は、あくまでオタクのまま、好奇心であふれた存在でありたい。それほど脳の中は未知であふれており、我々の日々の臨床活動から得られる知見そのものが、ニューロサイエンスを発展させる貴重な一歩なんだという事を楽しめる夢見がちな子供で居たいと祈ってこの会を企画させていただきました。皆様の御参加をお待ちしております。